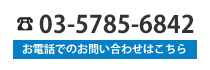人事制度の今昔
日本の高度経済成長を支えてきた終身雇用と年功序列は、バブル経済崩壊とその後の失われた30年のほぼ横ばいの経済社会において進行したのは、非正規雇用と成果主義でした。人件費を抑えて、価格競争戦略で収益を維持するために求められた軌道修正でした。
超高齢少子社会化による人口減少社会が急速に進み、若手の人手不足が問題視されるようになってきています。高度経済成長期の間もない頃に「縁故温情主義」を変革するために議論された「職務定義」は、有能な若手人材の採用や抜擢を目的として、欧米に倣って「ジョブ型-成果主義」の人事制度として、今日、改めて、導入が進んできました。
人は、コストなのか、投資なのか
高度経済成長期から現在まで、人への投資が重要であるという認識に変わりはありません。しかし、現在、人をコストとして扱うのではなく投資と考えた人的資本という考え方が広がってきています。
確かに、リカレント教育やリスキリング教育も、有能な人材の雇用や抜擢をすることも、投資と考えることはできます。しかし、今さらながら、人への投資を促進しようという政策が主張される背景にあるのは、新たな成長分野への職務転換を可能にして人手不足への対策としよう、新たな人材を育成して労働力を高め国際競争力を高めよう、非正規労働者が再就職できるようにして経済格差問題を解消しようといった経済的な意図があります。
そもそも人は社会的生きものであるとして見直す
しかし、人は経済的生きものである以前に社会的生きものです。システムの中で歯車のように決められたことを正しく刻みながら働き続けることは耐え難いことであり、そうして働かせること自体が人権問題にもなります。
一方、自分の意志で何をしなければならないかを考え、自ら創意工夫をしながら働くことで、人は達成感を得られ働き甲斐を感じながら働けるようになります。全体を俯瞰しながら、周囲の人たちとも協調して、その時その場で成すべきことを相互に決め合って、協働するようにもなります。社会的生きものとしてみた分業の仕組みは、経済的生きものとしてみた分業の仕組みとは、全くことなる在り様をなします。
経済的生きものとしての働き方 VS 社会的生きものとしての働き方
経済的生きものとして、報酬を原動力にして、決められたことを正しく行う働き方では、所定のものを超える結果を出すことはありえません。特に、「ジョブ型-成果主義」にあっては、規定を超えることを行うことは規範に反することにもなります。
社会的生きものとして、協調し協働して働く働き方は、働き甲斐を原動力として、周りの状況に応じて臨機応変に相乗効果を発揮しながら働くため、所定のものとして想定さたものを超える結果が得られる可能性があります。
人を社会的生きものとして捉えた 働き方/組織の在り様のモデル化
社会的生きものとして働く働き方をする組織の組織像は、以下のようになると考えられます。ここで、職責とあるのは、主に、企業内で企画業務や管理業務への責務を負っている人たち、あるいは、研究開発や設計に従事している人たちの職責を想定しています。
- 社会や組織全体の趨勢から今の現場で起きていることまでの一連の情報が、経営トップから現場担当者まで、情報の非対称性はなく、客観的でオープンに、遅延なく同時に伝達される
- 企業の存在意義に則して、組織の中で全員が、その情報の意味を共通に認識し理解される
- 情報の意味についての共通の認識と理解の下で、問題意識、採るべき行動の選択肢と判断基準が共有され、合意が形成される
- 経営トップのダイナミックケイパビリティ(#1)によって機能する組織でありながらも、オーケストレーションによって行動する組織ではなく、ティール組織(#2)でありながらも、組織システムによって経営トップから現場担当者まで様々な職務レベルでの意思決定が相互に循環しながら連鎖して行われ、フュージョンによって行動する組織である
- 一定の職責の中で「全体を俯瞰した視点で自律的に行動する」という職責定義(社会における取り組の優位性や影響力の発揮。単に、職務の定義ではなく、成果の定義でもなく、部門の立場を守り抜くでもない)のもとにエンパワーメントと双方向のエンゲージメントがなされ、経営と現場が一体となって行動し、経営環境の変化に対して柔軟に対応していく
- 報酬や昇格は、個々人が組織の中で負っている責任の大きさと、その負った責任を自ら果たしているかどうかという評価基準の下で決められる
現時点の社会環境の中で、こうした働き方や組織の在り様が実現可能か、職責の具体的定義は可能か、制度として抜け穴はないか(悪用されないか)、実現可能なリテラシーは整っているか、法制度と矛盾は生じないか、人権の視点から不具合はないか、どのような効果がどれほどあるのか計測可能であるか、といった点はこれからの検証テーマですが、一つのモデルとして考えています。
サステナブル・イノベーションズ株式会社 池邊純一
- D・J・ティース、菊澤研宗,橋本倫明,姜理恵訳、『D.J.ティース ダイナミック・ケイパビリティの企業理論』、中央経済社、 2019.10
- フレデリック・ラルー、鈴木立哉(訳),嘉村賢州(解説)、『ティール組織 マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』、英治出版、 2018.1.24