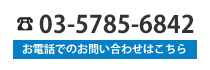先に、売上分析のテクノロジーについて当コラムに掲載しましたが、利益分析となると、状況は一変します。何故なら、利益にはコストを捉えるという作業が加わり、コストには原価や販売促進費や様々な管理費といった要素があり、業務の効率や品質が大きく関わってきます。当然のことながら、ロットサイズや在庫コスト、物流コストも捉えなければなりません。これを模式化して描いたのが「売上、利益、在庫の連鎖(History to Future 20151125-1)」です。
利益はまた、財務会計上は、粗利益/営業利益/経常利益/税引き前当期利益/純利益の概念しかありませんが、業績管理(管理会計)上は、限界利益、貢献利益などの管理など、更には、直接商品にかかるコストとして認識できない間接費や全社共通費を賦課したりして “大体これくらいかかる” といった把握しかできないのが実態です。しかも、これら様々なコストの計上時点も商品販売時点ではなく、月末締め時点になったりといった問題も生じで、日々タイムリーに把握することは不可能です。
より高い精度での把握のために、先人達は多大な努力を払ってきました。例えば、ロバート・S・キャプランはABCマネジメントという仕組みを提唱し、更には、長期視点と短期視点、財務と非財務、株主と顧客等のバランスをとりながら管理する BSC “Balanced Scorecard” とストラテジーマップの仕組みを提唱して、こういった問題の解決を図ってきました。
実際のビジネスでは、新商品、既存商品(成長期、成熟期、衰退期)が入り交じって展開されます。新商品は出荷数と実売上(いくらの単価でどれくらい売れているか(売れ残って店頭在庫になっていないか)が気になります。また成長期の商品は売れ行きと欠品による販売機会ロスが気になるところであり、売上成長率と在庫の回転率の状況がフォーカスされるでしょう。一方、成熟期になると、競合製品も市場に溢れて、低価格での販売競争に陥る可能性もあります。その意味で、本当に利益がでているのかを見るために限界利益(損益分岐点売上高)に焦点が集まります。クロージングを向かえる商品については、商品開発費を回収できたのだろうかという投資回収率も気になってくるものです。当然のことながら、新商品が既存商品の市場を食う共食い現象(カニバリ)も生じますので、その点も勘案していかなければなりません。「プロダクトライフサイクル別に捉えるKPI(History to Future 20151125-2)」参照。
本来、継続的に利益を確保していくということは、その時点での数字を表面的に捉えてどうこうするというのではなく、トレンドを受け入れる社会の変化をも勘案して、商品の売れ行きと販売価格の状況を把握しながら、次なる戦略を考えていかなければならないことなのです。
サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役 池邊純一